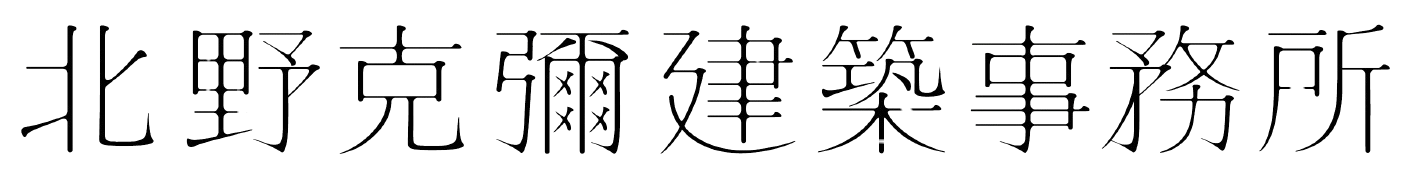雑誌を見たり、ネットを調べたりして旅を計画する。
旅は行ったことがないところへの計画だ。
未知に対する計画とはいったい何だろう。未知を知るために行くが、未知に対して計画をする。
一見すると矛盾を含んでいるように思う。なぜなら「未知」はまだ経験していないもの、わからないものなのに、そこに対して事前に「計画」を立てる。計画は秩序や予測に基づく行為であり、未知は予測不能や不確定の象徴だから。
旅行雑誌に載っている名所を事前にいくらでも調べることはできる。ただ調べすぎてしまえば、旅先での体験は単なる確認作業になってしまう。未知をすべて既知に変えてしまった旅は、驚きや発見を失い、その本質を損なう。ゆえに計画は未知を消すための道具ではなく、未知を迎え入れるための舞台装置であるべきだ。計画と余白、その相互関係こそが、旅を旅たらしめるのである。
家を一から建てるというには実際にやってみなくてはわからない。
強い信念を支えにしながら、終わりの見えない旅を歩むことにも似ている。
暮らしの計画は、いくらか未来への暮らしを包含する。
しかくいくら計画を立てても実際に暮らしが始まると計画と現実の暮らしとのズレが必ず生まれる。
時には我慢すれば計画した建築に合わせて計画した暮らしをすることもできるだろうが、それは暮らしに対する自然な態度とは思えない。それではお互いにあまりに窮屈かもしれない。
建築に必要なのは、すべてを規定することではなく、未知を受け止める余白を残すことである。
季節の移ろいや光の変化、家族の成長や趣味の変遷といった予測不能な出来事が、暮らしを豊かにする。建築はそれを静かに許容する器であり、旅と同じく「未知に対する計画」である。
計画と現実の差異が生まれるからといって、計画を疎かにする理由にはならない。むしろ差異があるからこそ、計画は意味を持つ。旅が道を誤ったときに地図が軌道修正を可能にするように、建築における計画もまた、現実とのズレを抱え込みながら進むための拠り所となる。計画は未来を固定するものではなく、未来を歩むためのコンパスになる。
家が出来たあとに暮らしという長い長い旅が始まる。喜びも悲しみも、予定外の出会いも、すべてがその旅を形づくる。建築は動かない乗り物である。行き先を決めるのは住まい手自身だ。その旅路にどのような風景が待ち受けているのかはわからない。ただ確かなのは、建築が静かにそこにあり、暮らしの旅を共に歩む伴侶であるということだ。