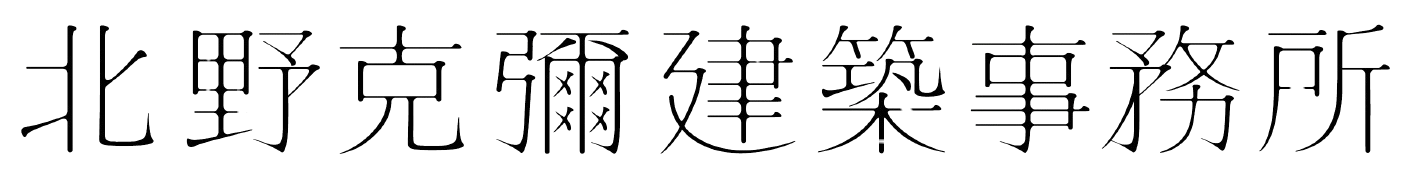1. 境界という人工の線
土地の境界は、いつ誰が決めたのかも定かではない線によって定められている。
その線は、私たちの土地を他人や公共の領域から切り分けるが、自然の中にはもともと存在しなかった。境界とは人間社会が生み出した「人工の約束」にすぎない。
私たちはそうした境界に則って、自分の領域を主張したり、他人の境界を感じたりする。法律上は土地所有の分割区分線として記録されるが、その実体は書類や共通感覚(コモンセンス)の中にしか存在していない。
より大きな視点でいえば、境界は個人の土地にとどまらず、組織や国というスケールにおいてもAとBを分ける線として機能している。その最小単位が「個人が所有する土地」という概念であるのかもしれない。
2. 漱石『こころ』の襖一枚
最近改めて漱石の『こころ』を読み直した。物語後半は先生による独白であり、読者は先生の一人称の告白を通じてしか出来事を知ることができない。そのため、親友Kの胸中は直接語られることはない。
先生とKは襖一枚で隔てられた部屋に住んでいた。先生はKの部屋を通って自室に行き来し、そこには現代的な「個室」の観念は希薄だった。襖は仕切りでありながらも、今日のように絶対的に閉ざされた私的空間を意味するものではなかった。
つまり、Kにとって本当の「私的領域」は物理的な部屋ではなく、内面の精神の中にしか存在しなかったのである。
やがてKが自死した夜、主人公は襖が二尺ばかり開いていたことでその死に気づく。襖の「開き」は、Kが死によって心に閉ざしたものを吐露した暗喩のようにも読める。襖という舞台装置を介して、先生とKの精神的・物理的な境界が示されているのだ。
3. 子供の頃の無境界感
境界や領域について思い返すと、子供の頃、他人の家の塀はただの通路であった。塀の上を歩いて、どこかへ行くための道として使っていたのだ。そこに「越えてはならない境界」という意識はなく、世界はまだ流動的で、すべてがつながっていた。
さらに言えば、赤ん坊は生まれてすぐの段階では「自己」と「他者」を区別できないとされる。母親は自分の一部として体験され、授乳や抱擁はそのまま自己の延長であった。世界はまだ一つであり、「私」と「あなた」を分ける線は存在していない。
やがてこの未分化の状態から、自己と他者の分別が芽生え、さらにそこから「自己の領域」と「他者の領域」へ、「自己の所有」と「他者の所有」へと展開していくのだろう。その観念はやがて人格のない物質にまで適用され、モノの所有へと広がっていく。
4. 大人になって芽生える境界感
大人になると、かつて通路だった塀は「絶対的な壁」として立ち現れる。門は「領域の入口」として、強烈に私と他者を分け隔てる象徴となる。
鉄の重い扉であろうと、襖のように軽い扉であろうと、そこに「領域の重さ」を感じるかどうかは、物質そのものではなく、自分が受け継いだ文化や慣習、そして内的な経験によって決まる。かつて境界を意識せずに過ごしていた日々が、今となっては嘘のようである。
5. 境界の真の所在
こうして見えてくるのは、境界とは外界に固定された線ではなく、私たちの内に形成される感覚であるということだ。
子供にとって境界は存在しなかった。『こころ』に描かれた襖のように、現代であればスマートフォンという装置が同じ役割を果たしているのかもしれない。そこでは心の奥にある「私」が、薄い境界を通して他者に漏れ出す。
私たちは慣習や文化に支えられた「境界の感覚」を内面に深く刻み込み、他者の領域を強く感じるようになったのである。
6. 結び
境界とは物理的な線ではなく、慣習や文化、そして私たち自身の内的経験が形づくる心理的構築物である。
その意味で境界は自然には存在せず、人の心の中に生まれ、人の心の中のもので重さを持ち、物質に適用されている。