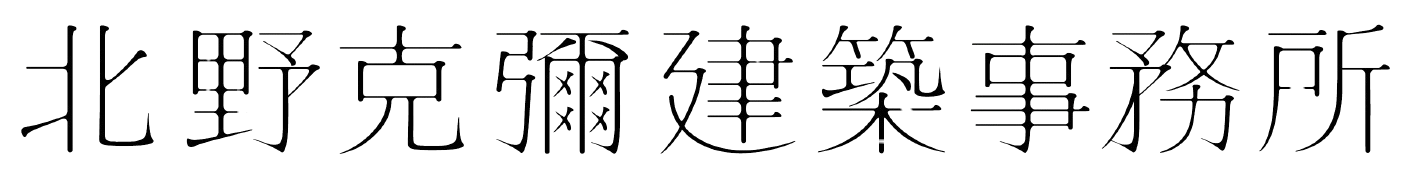高校時代、私は美術クラスのある学校に通っていた。
当時は絵を描くのが好きだったので特に将来のことも考えずにこの高校に進学した。
その高校を志望した理由は驚くほど単純で、自分が普通科の高校に通い中学校の延長の授業や科目を学ぶことに対してほとんど興味がもてなかったことにあったからだった。
今思えば、これまでの人生の選択の決断も似たような単純な理由が多い。そうした決断の仕方はすでにこの時に始まっていたのかもしれない。
高校は自宅から電車とバスを乗り継ぎ一時間かかる場所にあった。
このクラスは一学年に一クラスしかないため三年間同じクラスであった。
授業は普通の一般科目に加えデッサン、油絵や彫刻などの専門科目に多くの時間を割いていた。
デッサンはクラスでも上手い方ではなかったが、デッサンの時間は好きだった。平日は授業が終わってから7時くらいまで石膏像のデッサンがあり、いつも自宅に帰るのは20時を過ぎていた。
朝早く家を出たときには、誰もいないデッサン室で絵を描いたりするのがとても気持ち良かった思い出がある。
デッサン室は他の教室にくらべ天井も高く広い教室で、北面には大きな窓があった。窓からは自然光が入りデッサン室はいつでも明るい場所だった。北側の窓は一日中安定した光のためモチーフの陰影が変わらないためデッサンに適した環境だった。
壁際にはギリシャ彫刻の石膏像が並んでいた。
吹抜けのある廊下ではサモトラケのニケの石膏像も置いてあった。
カッターで鋭く削った鉛筆を使って、線を幾重にも重ねる。あるいは鉛筆を寝かせて描き、影や光の濃淡、もしくは物の奥行を表現する。練り消しは消しゴムとは違う。描いたものを消すものではない。鉛筆と同様に平面の中に立体を表現するための道具であった。
絵の上手さは手先の器用さよりも、モノの見方のほうが大きいように思う。写実的であれ、デフォルメであれ、観察なしには達成しえない。
デッサンは主観と客観を行き来する行為だと思う。自分の描いた線と対象の状態の比較し、描いた線が対象に近しいものになっているかを観察する。あるいは描いた線が全体の画面の中で他の線との関係性に調和がとれているか、など。
石膏像と向き合い、鉛筆の線を重ねる時間は、ただ絵を描くだけではなく、ものを観察し、自分の感覚を問い直す時間だった。
そうしたモノの観察の仕方はここで養われたと思う。同時にそのことは自分自身の価値観の由来になっているのではないかと思っている。
その体験が、いま建築に向き合うときの姿勢や価値観の原点になっている。