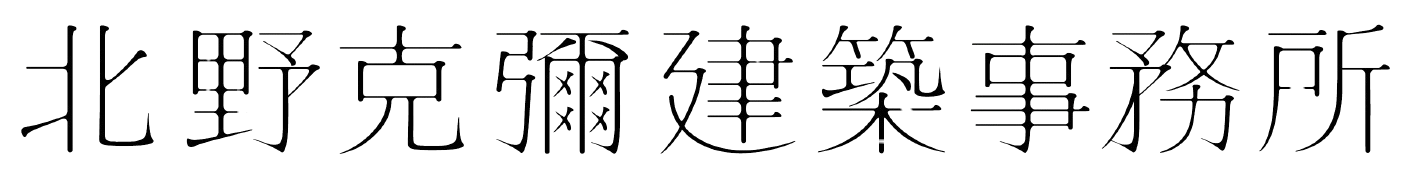家の居心地の良さはどこから生まれるのか。
私はそれを「構造」「環境(性能・設備)」「意匠(素材・プロポーション)」の三つの要素から成り立つものと考えている。
構造
建築のもっとも根本にあるのは骨組みである。構造が確かであることによって、人はその空間に安心を感じることができる。安心感は数値に表れにくいが、地震の多い日本においては、人々が無意識のうちに最も求めている感覚であるといえる。
環境
環境とは、人が空間に身を置いたときに肌で感じる快適さや不快さである。風が通り抜けたときの爽快さ、冬に温かい部屋で過ごす安らぎ。これらを支えるのが性能や設備である。断熱や気密の質が高ければ、暮らしの中から「不快さを忘れさせる」ことが可能になる。夏の夜、寝苦しさから解放されること。冬の朝、足元の冷えを感じないこと。その積み重ねが居心地の基盤となる。
意匠
意匠は、視覚や触覚を通して感じられる部分である。素材や形の美しさ、空間の比率の心地よさ。木の床の温もり、タイルの素朴な表情、光が壁をなぞるときの陰影。意匠は最初に人の感覚を引きつけ、日々の暮らしを豊かにする。
世間一般に「デザイン」と呼ばれるものは意匠に偏りがちである。どんな色にするのか、どんなハンドルにするのか、それらは空間全体のスタイリングやコーディネートといえる。しかし私にとってのデザインとは、さきの三要素をバランスよく束ね、最小公倍数を見つける行為にほかならない。
例えば、複雑に入り組んだ平面であっても、構造計算を施せば耐震等級三を満たすことは可能である。しかし、もともと単純な平面であれば形自体がすでに安定性を備えている。その上で計算による裏付けを与えることが、確かな安心感につながる。
窓ひとつを考えるときにも、三つの視点が交錯する。意匠の観点では、気持ちよいプロポーションを探る。性能の観点では、西日の侵入やコールドドラフトを避けるために位置を調整する。構造の観点では、まずは壁を優先的に考え、窓をどこに設けるかを決めていく。設計の過程では、これらの思考が常に同時に進行している。
実際に平面図を描くとき、私はスケッチを重ねながらも背後で構造的な安定性や断熱性能を意識している。たとえ図面上には表れていなくとも、常に構造と環境と意匠のバランスを探る思考が並走しているのである。
そしてその積み重ねの先にあるものが、「居心地」である。
それは数値や図面に還元できないものであり、空間に身を置いたときにふっと感じる安心感である。
夕暮れ時、窓辺で子どもが本を読み、柔らかな風がカーテンを揺らすとき。
冬の朝、家族がダイニングに集まり、温もりのある空気の中で自然と笑みがこぼれるとき。
そうした瞬間を支えるために、構造・環境・意匠を束ねることこそが建築のデザインである。居心地の良さとは、理屈を超えて人を包み込む感覚であり、私が建築を通して追求し続けたいものである。