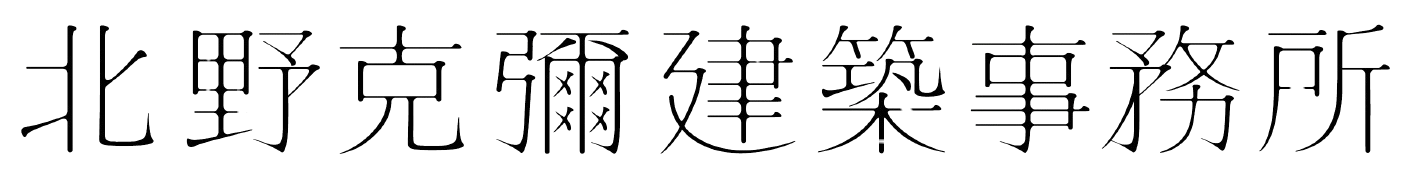いい家を考える。
断熱性能の数値でも、見た目の美しさでも、面積でもない。
住む人が安心して幸福に暮らせるのなら、それらはあまり関係ないのかもしれない。
いい家をつくりたいと常々考えている。
しかし、そもそも「いい家」とは何かと考えると、思考がいったりきたりする。
いい家は、設計者が決めるものではないのかもしれない。
器を器単体で評価しても、それは本当の器の価値ではない。
そこに料理が盛られて初めて器の意味が生まれるように、
家もまた、住む人がいて初めて完成する。
どんな生活がそこにあるかを想像する。
ここに窓があったら気持ちいいだろうか。
ここに飾る場所があれば素敵だろうか。
自分の家ではないけれど、自分が住むように考える。
私は家の半分のところと、そこから少し先の補助線を引く程度までしかつくれない。
その先――補助線の外側は、住む人の領域だ。
そこから先は、暮らしの時間とともに描かれていく。
生活のある家が好きだ。
そこにはその家族の人柄や文化が見える。
家族は文化の最小単位だ。
家ごとに小さな決まりごとがあり、
それが空間の中に可視化されている風景は、
異文化をのぞくように新鮮で、美しい。
居心地がよかったり、性能がよかったりするのは、
家の最低条件かもしれない。
けれども、そこではぐくまれる家族の歴史や文化が、
家をただの器から、暮らしの風景を盛る器へと変えていく。
家の価値は、時間の経過とともにゆっくりと深まっていく。
家族の記憶が重なり、季節の光が染み込み、
そこに住む人の気配が少しずつ家のかたちを変えていく。
その積み重ねこそが、「いい家」をつくるのだと思う。